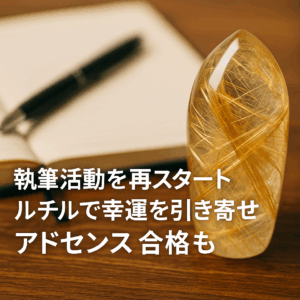人に指示を出して動かす
失敗の連続で何も思うように行かなかった
そしてこの1-3月にできた貴重な経験がこれ。
20人近くのメンバーを動かす経験ってやりたくてもそう簡単にはできない経験だけど、それを約1年に渡って経験させてもらえた。
非常にありがたくて、貴重な経験だったけど失敗の連続でめちゃくちゃ頭を悩まされた。
こっちは伝えて指示したと思っていても、相手がそれを指示だと捉えていなかったり、自分が思っていたクオリティの物が出来上がってこなくてそこから修正の指示などを行う必要があって、余計に時間が掛かったり。。。
やる気があるけど、スキル不足で成果物の質が低い人はまだよい。
後半には追加メンバーが何名かいて、追加メンバーのやる気が低く明らかに手を抜いてきているメンバーもいた。そういったメンバーにどう接していくかも悩みまくった。キャパオーバーだから手伝ってもらいたいし、積極的に参加しているメンバーもいる手前全体の士気を下げる可能性もあるからしっかりやってもらいたい。だけど、何度注意して指示してもかわらない。それに納期もあるから気長には待てないから、もうそのメンバーから仕事ぶんどって期待せずに自分で片付けていったほうが早いんじゃないか。とか本当に色んなことを考えさせられた。
すっごい考えに考えて答えがでなかった結果、MTGの時に結構きつい口調でみんなの前で指摘してしまったこともある。相手も忙しい時間を使って頑張ってくれている。という前提をすっとばして、自分の感情だけで相手に接してしまったのは本当に反省。それは今でも覚えているし、申し訳ない気持ちでいっぱい。
人を動かす方法で学んだこと
そんな失敗ばかりで試行錯誤しながら、自分の中でセオリーみたいなのもいくつか出来た気がする。
まずは、指示するときは相手のレベルに合わせて具体的に指示をするか方向性だけ提示するかを使い分けること。
これは結構大事だと思う。こちらから指示した内容を、思ったレベルで仕上げてくれる人とえ、そのレベル?と悪い意味で期待を裏切ってくる人の2パターンが存在すると思う。前者の場合は、考えるスキルとかの思考レベルが一定高いと思う。そういった人には、ちょっと雑にこれやっといて!とかの指示でも全然行ける。むしろ、この人たちに事細かにやることを指示するのはいけてないと思う。それは説明工数もそうだし、別の観点でもそう思う。別の観点でいうと、超具体的に指示してしまうことでそれ以上のことが生まれづらくなるということ。自分が考えているものは出来上がってくるとおもうが、自分にはなかったアイディアを盛り込む隙をけしていることにもなる。そうすると自分の考えが史上最高のものだったらいいけど、もっと他にも可能性ある場合は非常にもったいない。だから、この手の人にはある程度抽象的に指示をして、彼らの脳みそも借りることがベストだと学んだ。
一方で、期待していたレベルの内容になっていない場合は要注意。
このパターンはやる気がなくて手を抜いている・時間がなくて取り掛かれなかった・スキル不足の大きく3パターンくらいに分類される。最初の2つはなんとなく話していればわかるので、問題はスキル不足の方。この人に対して抽象的な指示を出しても、指示の背景や目的などを考えることが出来ずに成果物が期待を大きく下回る可能性が高い。そういった時は、さっきとは逆手超具体的に手順を伝えるくらいの粒度でやることを指示することが大事だと学んだ。
でも、これには落とし穴があってこれを口頭で指示をすると具体的に指示したつもりがまだ相手に伝わってないってことも発生する。
だから自分がやったのは事前に、イメージというかサンプルをつくってこのフォーマットで中身を考えてきてって依頼をしていた。こういった形で相手のレベルに合わせて指示粒度をかえることが大事だと学ばされた。
相手のモチベーションを下げない
モチベーションを上げるのも大事だけど、モチベーションを下げないのも大事だなって感じた。
モチベーションを上げるのって正直難易度が高いと思う、モチベーションが上がるタイミングって人によって違うし上がったことを感じにくいし、、、でもモチベーションが下がるときって、みんな同じ人間だから「怒られた時」とか「めんどくさいとき」「忙しい時」「やる理由がわからない時」とか共通していると思う。しかもモチベーションが上がった時と逆で下がった時はすっごいわかりやすい。
モチベーションが上がったら加点ポイントで、当初予定したよりもいいものができる可能性がある。
モチベーションが下がったら減点ポイントで、作りたい水準のものが作れない可能性がある。
こう考えると、モチベーションを下げないようにして今の水準を頑張ってキープすることが組織の生産性においても重要なんだと思う。
そう思ってからは、相手の意見を聞いてやらされている感じをなくしたり、やる目的とか意義をしっかり伝えたり、感謝の言葉をしっかり口にしたり、人に指示してるだけで苦労してるの俺だけじゃんって思わないように率先して手を動かして汗をかいた。
こういったモチベーションを下げないような取り組みも組織を率いる上では必要なんだなった学んだ。
そして嬉しいのが、今回だけかもしれないけどモチベーションを下げない取り組みをしているとモチベーション上がる人が多かったこと。後半追加メンバーとか短期間の人のモチベーションを下げないようにするにはどうすればいいかはまだこれから学んでいかないといけないことだ。